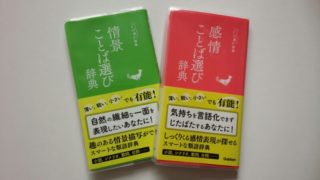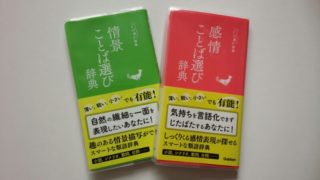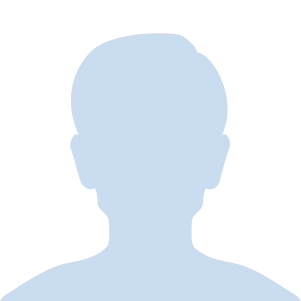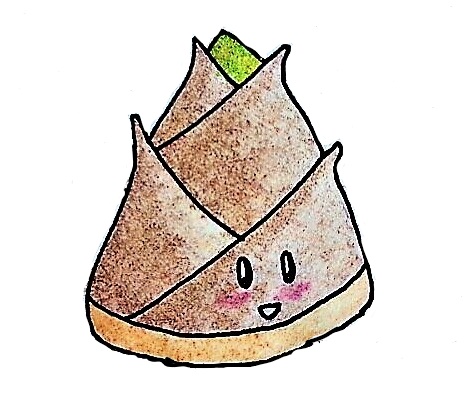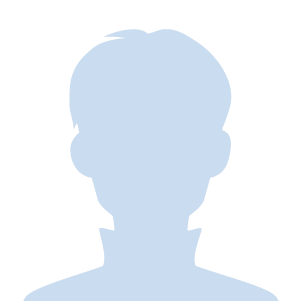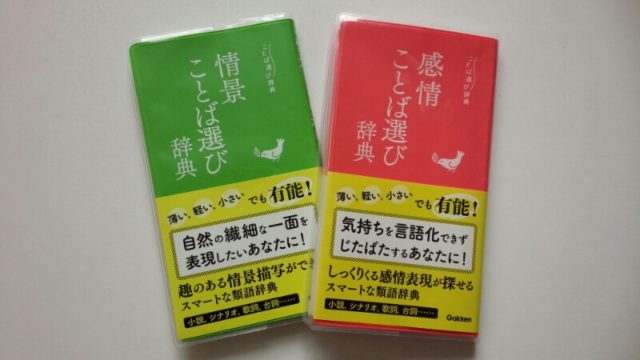今回は世界観づくりの役に立ちそうな歴史の出来事をまとめました。
学校の授業ではテストに出る部分にマーカーを引きますが、ここではファンタジーに出てきそうな設定や語句を赤文字で記しました。ぜひご活用くださいませ。
古代ギリシア時代(紀元前30世紀~)


古代ギリシアといえばギリシア神話ですが、他にも異世界ファンタジーの参考にできそうな部分があるのでご紹介しましょう。
お宝がありそうな遺跡・神殿
ファンタジー世界ではダンジョンとして登場することが多く、お宝が眠っていそうな石造りの遺跡。ギリシアにはモデルに最適な場所が数多く残っています。
英雄アトレウスの宝庫があるミケーネ遺跡、アポロン神殿があるデルフォイの遺跡が有名でしょうか。世界史の教科書によく写真が載っているのはパルテノン神殿。首都アテネで市民の総会や交流の場として用いられた場所です。
特にデルフォイは聖域と言われ、アポロン神殿では巫女が神様の言葉を伝える神託(しんたく)が行われました。争いごとなどの重要な判断は、神様の言葉で決めていたんですね。
都市の発展を支えた奴隷制度
ラノベタイトルでもたびたび見かけるようになった奴隷。
という個人的疑問はさておき、古代ギリシアにおいての奴隷制度は当たり前で、都市の発展を支えた存在でした。
紀元前5世紀前半のアテネ人口構成比をみると、市民が半数に対して奴隷は3割半ほど。奴隷を持つ市民が多かったようです。
奴隷となるのは債務を返済できなくなった者や争いでの捕虜、商人が別の国から調達する場合もありました。
仕事は炊事洗濯といった主人の世話役から、農作業や鉱山労働などさまざま。立場も都市によって異なります。
都市を防衛する市民たち
他都市の攻撃から防衛するため、市民は鎧・兜・盾を装備して重装歩兵となりました。
全員が固まって長い槍を構えて前進する戦法が取られました。この戦い方を密集隊形(ファランクス)と呼びます。戦いで活躍した市民は政治での発言権も強くなりました。
しかし装備は支給されるものではなく、それぞれが身銭を切って調達していたそうです。
争いの長期化により農地が荒れたり、市民が没落すると防衛の戦力確保が難しくなっていったため、傭兵の力を借りることも多くなりました。やはり餅は餅屋ですね。
かっこよく聞こえる五百人評議会
アテネの政治は民会と呼ばれる直接民主制で、18歳以上の全男性市民が会議に参加して多数決を取っていました。主に争いごとに関する審議や、将軍の選出が議題です。
その後の改革で新たに五百人評議会という組織が設立。10の部族から各50人を選出し、民会で話し合う議題の事前審議や行政を担当しました。
現在の日本でも100人委員会のように地方自治の実現を目指す組織が各地にあるようです。ちょっとかっこよく聞こえる名前じゃないですか?
ローマ世界(紀元前753年~)
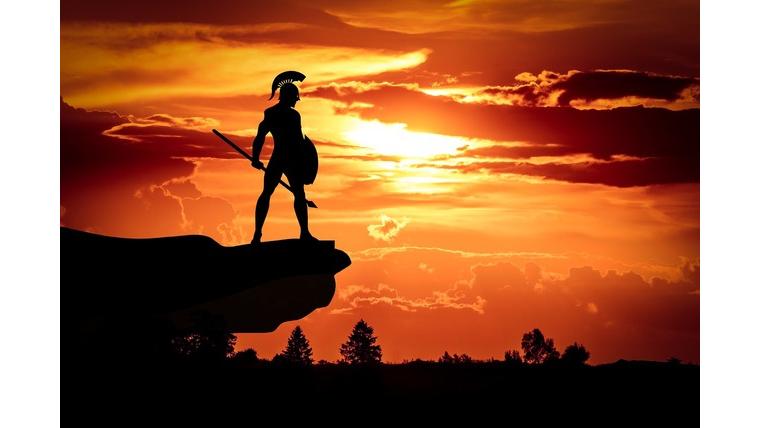
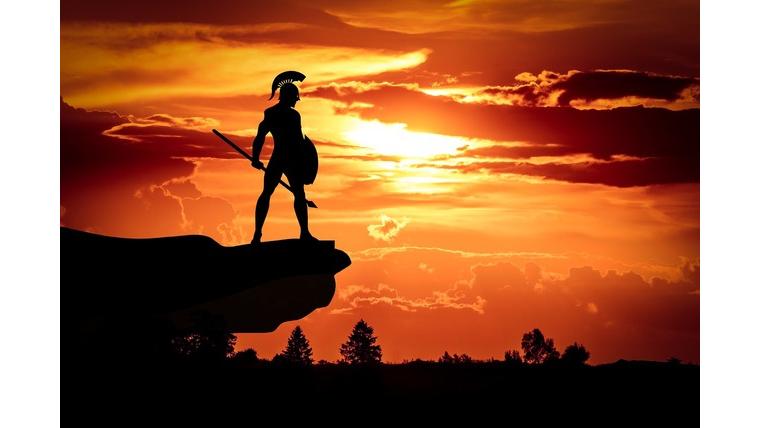
狼に育てられた双子の兄弟、ロムルスとレムス。その兄ロムルスが成長して、紀元前753年に都市国家ローマを建国したという伝説が残っています。
歴史上でも有名なローマ帝国ですが、ファンタジーのモデリングにもたくさんの史実が参考にされています。その仕組みをお話しましょう。
領土拡大の工夫
ローマは領土を拡大して帝国を築きます。地中海沿岸全域からブリタニア(現在のイギリス南部)やメソポタミア(イラクの一部)など、広い領土を持っていました。
しかし支配が拡大するほど統治は難しくなります。そこで都市ごとに別の条約を結んで差別化する分割統治を行い、征服地の反乱を抑制しました。イタリア半島は大きく三種に分類されます。
- ローマと同じ市民権のある『植民市』
- 税金や兵役、市民権や租税義務はあるが政治の投票権がない『自治市』
- 市民権がなく兵役の義務がある『同盟市』
その他の領土は『直轄地』や総督が治める『属州』に区分けされ、後者は特に重い税金を課していました。こうして国はどんどん大きくなります。
共和制では元老院が最高機関


ロムルスから続く王政国家だったローマですが、紀元前509年に独裁政治を執っていた王を追い出して共和制となりました。しかし政治に参加するのは市民全員ではなく貴族のみ。ローマは「貴族(パトリキ)」と「平民(プレブス)」の階級に分かれていたのです。
君主を持たない時代は元老院(げんろういん)が最高の決議機関となっていました。おじいちゃんとおばあちゃんで構成されていたわけではありませんよ。
元老院は日本でいうなら国会のような機関。しかし任期がないため権限を蓄積しやすく、議員も身内で集めやすいので、必然的にローマの最高機関になりました。
実はこの頃から騎士(エクイテス)という身分がありました。一般的に鎧に身を包んだ戦士……ではなく浮遊市民層のことです。地域の統治者に変わって徴税をおこなったり、商業に従事して富を蓄えたりしていました。
元老院の国家支配に対抗すべく、軍人のカエサルとポンペイウス、クラッススが秘密裏に盟約を結びました。
しかしクラッススが遠征で命を落とし、ローマの内乱でポンペイウスはカエサルに倒されます。権力を独占しようとするも元老院派のブルータスによって議場で命を落としました。
腹心だと思っていた相手に裏切られたカエサルが最後に残した「ブルータス、お前もか」は屈指の名台詞です。
その後、カエサルの養子であるオクタヴィアヌスが地中海一帯を統一し初代皇帝に即位。ローマは共和制から帝政に移行します。子供が親の悲願を達成、ドラマ性を感じますね。
皇帝が統治する時代に移行
紀元前27世紀。アウグストゥスの称号を得たオクタヴィアヌス(ややこしい)による元首政が始まりました。一般的にはここからがローマ帝国の時代と言われています。
特に紀元後96年~180年は安定していて、全盛期を迎えていました。
この時代の五人の皇帝を讃え五賢帝時代(ごけんていじだい)と呼ばれています。治安がいいので人や物資の往来も多く、経済はまわり文化が発達しました。
235年になると軍人から推挙されたマクシミヌス帝が即位。皇帝は軍人出身者よって占められ軍人皇帝時代に突入します。軍隊の発言力が強くなり、元老院も手を焼きました。
それから約50年後、貧しい身分から軍人に成り上がったディオクレティアヌスが皇帝の座に就くと政治体制は一変します。
今まで政治を担っていた元老院に代わり、皇帝がすべて独断で遂行。さらに皇帝を神の化身と崇めさせ、権威を確立させました。専制君主制の始まりです。
さらに帝国を四分割し、皇帝と副帝の計四名で統治を始めました。これを四帝分治(していぶんち/テトラルキア)といいます。
以降は政治体系が不安定になり395年、とうとうローマ帝国は東西に分裂しました。
ファンタジーで人気の施設といえば闘技場


ファンタジーでも登場頻度の高い建造物といえば円形闘技場(コロッセウム)。戦いの舞台として描かれることが多い場所ですが、現実で建設されたのは80年なんですね。
約50000人を収容できる娯楽施設として、剣闘士たちのバトルや、人間と猛獣の戦いが見世物として披露されていました。
以外?と発達していた生活インフラ
ローマ時代の初めて建設されたのがアッピア街道で、もとは軍隊用の道路として利用されていました。路面には石が敷かれ、一定距離ごとに目印(マイルストーン)を設置。
生活水は水源地の水を貯水槽に留めておき、水道管を通して公共浴場や噴水に供給していました。
一般市民は共同水場から水を汲むことで調達していましたが、裕福であれば自宅まで水道を設置していたとか。この辺りの知識は貧富の差を表す描写に使えそうです。
中世ヨーロッパの世界(476年~)


中世が具体的にいつから始まるのか? 実はしっかりと決まっていません。
一般的にはローマが東西に分裂した395年、西ローマ帝国が滅亡した476年あたりからスタートとされているようです。
中世といえば騎士! 階級制と序列の仕組み
馬に乗り鎧に身を包んだ騎士が活躍するのは9~12世紀ごろ。
国王・諸侯・家臣の主従関係による封建制度が出来上がってからです。社会は階級制で、最上位の国王から諸侯や司教、騎士、最下位の農民・農奴と序列が出来上がっていました。
騎士は主君に軍事的奉仕で忠誠を誓い、主君は領地を与え保護していました。
主従関係を結ぶにあたっては臣従礼(しんじゅうれい)という儀式を行い、騎士の象徴である剣を授けられていたそうです。
1096年以降、カトリック教会の諸国が聖地奪還のために十字軍を派遣。
ヨーロッパからの巡礼者や聖地を外勢力から守る目的で誕生したテンプル騎士団は教科書にも出てくるほど有名。
ギルドは盗賊だけのものじゃない


ファンタジーには付き物といってもいいほど登場するギルド。そのほとんどは盗賊ギルドのような気もしますが、そもそもギルドってなんなんですかね?
簡単にいうと、同じ職業の人間が集まって作った組合がギルドです。大工や肉屋、染め物職人のギルドもありますし、ファンタジーに使えそうなら甲冑師のギルドでしょうか。
13世紀には3桁を超えるギルドが存在し、15世紀のヨーロッパ大都市には大抵ギルドがあったそうです。
力を持つギルドは集会場(ギルドホール)を持っており、専用の紋章を掲げていたとか。
ギルド本来の存在理由は組合員の賃金や権利の確保。仕事に関する価格や水準を規定し、公平かつ競争しないようにしました。日本社会の労働組合にちょっと近い感じがします。
昔の大学では習うことは三学四科
都市の発展とともに大学も設立されました。学生が主だって運営し、自分たちの権利を守る体勢はひとつのギルドだと言えます。
ファンタジー世界の授業は魔法と歴史の科目がほとんどですが、この時代の学問は一般教育として文法・修辞・論理の三学、算術・幾何・天文・音楽の四科が基礎科目。
これらの過程を修めると専門教育として神学部・医学部・法学部に進学できます。
ステンドグラスが目を引く教会建築の参考も有名


教会もまたファンタジーに登場頻度が多い建築物ですが、有名な形といえば12世紀の北フランスを起源とするゴシック様式。先のとがった槍のような屋根に、光をたくさん取り入れるための大きな窓が特徴です。
ステンドグラスも芸術的なものが多くなりますが、背景には金属やガラス産業の発展がありました。物流や技術あってこその文化なんですね。
近世ヨーロッパの時代(15世紀~)


大航海時代の到来やルネサンスの時代が近世の始まりだと言われています。
と思う方もいらっしゃるでしょうが、実は一番ファンタジーの世界観に近い時代かもしれません。
国王が権力を持ち、政治を支配する絶対王政が現れるのはこの時代。「国に王様がいる」ファンタジーなら当たり前の設定は、近世ヨーロッパがモデルとして近い気がします。
強力な装備アイテムがぞくぞく出現


強力な矢を発射できる巻き上げ式石弓や、弾丸を発射できる火器によって、薄い鎧は簡単に貫けるようになりました。
そこで全身を厚い金属で覆う板金鎧(プレートアーマー)が開発されるのですが、値段が張るので作るのも買うのもままなりません。
やがて戦場では槍を持ち軽装備で腕が立ち、装備の充実した歩兵が活躍するようになり、馬に乗った騎士は衰退していきました。
海の冒険もこの時代がベスト
世界三大発明のひとつである羅針盤が登場する近世は、海路での交易が一気に広まった時代でもあります。
海を渡る場面が出てくるなら近世の船や航海をモデルにすると、物語が膨らむかもしれません。
まとめ
ファンタジーで参考になりそうな部分を抜粋して紹介しました。現実世界の仕組みなので、創作アイデアの基盤にするには十分な根拠とリアリティが生まれると思います。必要な部分を上手く利用して、素敵な世界観を作り上げてください。
ここまでご覧いただき、ありがとうございました。
今回の参考文献
- 山北篤(2010)『ゲームシナリオのためのファンタジー辞典:知っておきたい歴史・文化・・お約束110』ソフトバンククリエイティブ.
- (2017)『山川 諸説世界史図録(第2版)』木村靖二・岸本美緒・小松久男監修,山川出版社.
- ラングリー,アンドリュー(2006)『中世ヨーロッパ入門』池上俊一監修,あすなろ書房.
- ディクソン,フィリップ(2008)『騎士と城』樺山紘一監修,鈴木豊雄訳,昭文社.